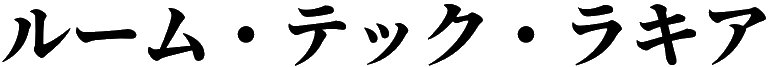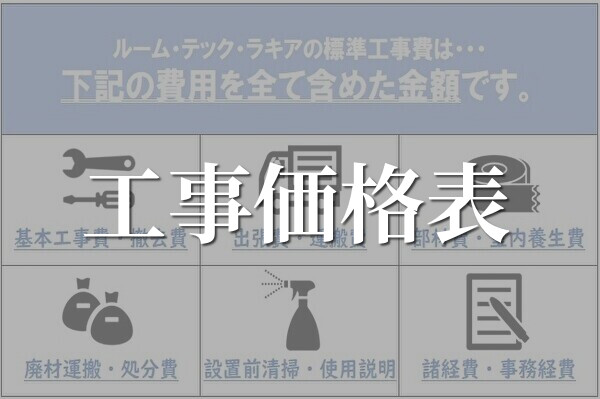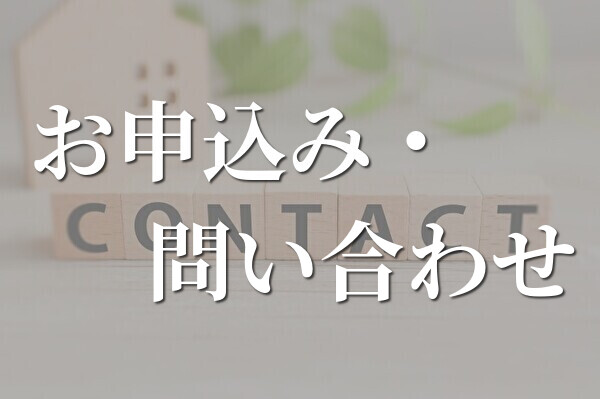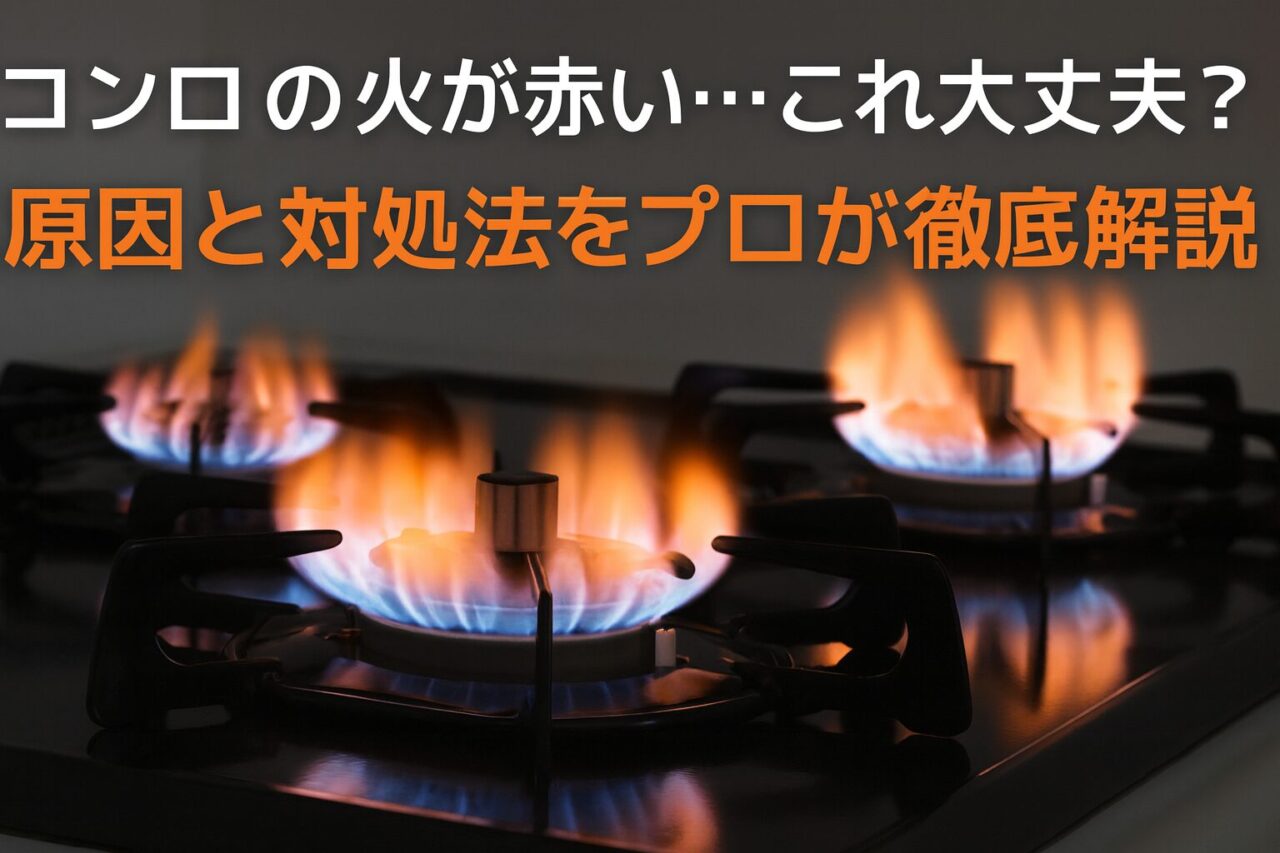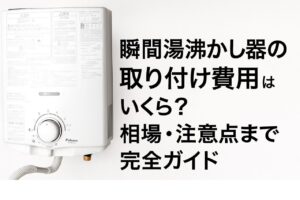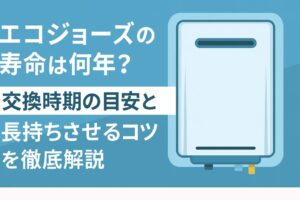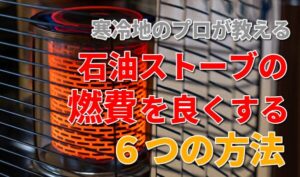はじめに:コンロの赤炎は異常のサイン?

ガスコンロの炎が青くなく、赤くチラチラ揺れているのを見たことはありませんか?
「冬だから?」「ガスの質?」と思う方も多いですが、実はこれ、燃焼状態が悪化しているサインの可能性があります。
赤火(あかび)は、不完全燃焼や酸素不足、バーナー内部の汚れが原因で起きることが多く、放置するとススの発生・一酸化炭素(CO)発生リスク・機器寿命の短縮につながります。
特に寒冷地では、換気不足や外気温による燃焼空気の取り込み不良が重なりやすく、冬場に赤火が目立つという現象も珍しくありません。
ここでは、家庭でよくある赤火の原因と対処法、そして放置した場合の危険性を、施工現場の視点からわかりやすく解説します。
ルーム・テック・ラキアでは、ガス種・キッチンの形状・家族構成に合わせた最適なビルトインコンロ提案・工事を行っています。
ガス接続や天板サイズの調整、古い機種の撤去までワンストップ対応。有資格者による安全施工をお約束いたします。
「火がつきにくい」「コンロの選び方がわからない」などのお悩みもお気軽にご相談ください。
 松本
松本お気軽にお問い合わせください!


赤火とは?正常な「青火」との違い


一見、炎の色は“気まぐれ”のように思えますが、実は燃焼状態そのものを映し出す鏡です。
ガスコンロの炎が青いのは、ガスと空気(酸素)が理想的なバランスで混ざり合い、完全燃焼している証拠。
逆に炎が赤やオレンジに見える場合、それは燃焼に必要な酸素が足りず、ガスが燃え切っていない=不完全燃焼の状態を示しています。
この違いは単なる「色の変化」ではなく、安全性・効率・環境負荷のすべてに関わります。
赤火のまま使い続けると、ガスが無駄に消費されるうえ、スス(煤)や一酸化炭素(CO)が発生しやすくなり、健康や機器にも悪影響を及ぼします。
特に冬場の閉め切ったキッチンや、バーナー部分が汚れた状態では、赤火が発生しやすくなるため注意が必要です。
実際の炎の見え方を比較すると、違いは一目瞭然です。
| 炎の色 | 状態 | 主な原因 | 対処の目安 |
|---|---|---|---|
| 青い炎 | 正常 | 酸素供給が十分 | 問題なし |
| 赤い炎 | 不完全燃焼 | 空気不足・汚れ・換気不良 | 早めに点検を |
| 黄色っぽい炎 | スス発生 | 酸素不足がさらに進行 | 使用中止・要点検 |
現場では、赤火の炎は「揺らめきが大きく」「鍋底に黒いススが付着しやすい」という特徴があります。
一方で青火は安定して静かに燃え、鍋底がきれいなまま保たれるのが正常な状態です。
つまり、炎の色はガス機器の健康状態を示すサイン。
色が変わったら、まずは燃焼環境を疑うことが大切です。
主な原因①:バーナーキャップや火口の汚れ
赤火の原因として最も多いのが、バーナーキャップや火口(ひぐち)の汚れ・目詰まりです。
ガスコンロの炎は、バーナー内部でガスと空気を混合し、無数の小さな穴から均一に噴き出すことで「青く安定した火」を作り出しています。
ところが、この穴のどれか一つでも油汚れや煮こぼれで塞がると、ガスと空気の混ざり方が不均一になり、結果として一部の炎だけ赤くなったり、全体が不完全燃焼に傾いたりするのです。
特に日常的に炒め物や揚げ物をする家庭では、油煙が少しずつバーナーに付着し、気づかぬうちに内部にまでこびりついていきます。
表面はきれいに見えても、キャップを外すと黒く変色したススや焦げつきがびっしり──ということも珍しくありません。
これらの汚れが空気の通り道を塞ぎ、赤火の発生を助長してしまうのです。
現場では、次のような特徴が見られる場合、バーナー清掃のサインと判断します。
- 炎の先がオレンジ色に揺らぐ
- 鍋底が黒くなりやすい
- 点火後の炎が安定するまで時間がかかる
- 使用中に“パチパチ”と音がする
これらの症状がある場合は、まずバーナーキャップを外しての清掃を行いましょう。
歯ブラシや竹串を使って火口の穴に詰まった焦げや油を取り除くことで、空気とガスの流れが正常化し、炎が再び青く安定することが多いです。
ただし、10年以上経過したコンロでは、熱による金属変形や腐食で穴の径が変わり、清掃しても改善しないことがあります。
その場合は、部品交換または本体交換を検討するのが安全です。
主な原因②:換気不足・酸素不足
家庭用コンロでは、通常の使用環境で酸素が足りなくなるほどの換気不足はほとんどありません。
しかし、調理空間が狭かったり、換気扇を止めたまま長時間使用した場合など、空気の流れが滞ることで燃焼が不安定になることがあります。
このようなケースでは、炎の一部が赤くなったり、揺らぎが大きくなることがあります。
特に、壁に近い位置で鍋を複数置いたり、レンジフードの吸い込みが弱い状態では、
コンロ周囲の空気がよどみ、ガスと酸素の混合が乱れる=赤火が出やすくなる傾向があります。
この現象は機器の故障ではなく、一時的な燃焼環境の悪化によるものです。
次のような方法で改善が見込めますので、赤火が発生した場合に気をつけておきましょう。
- 調理中は換気扇を常時運転する
- コンロまわりに物を置きすぎない
- 鍋やフライパンを複数口同時に使用する際は、奥側を避けて空気の流れを確保する
- レンジフードフィルターを定期的に清掃する
これらを行っても赤火が改善しない場合は、燃焼部内部の汚れや経年劣化が原因の可能性があります。
その場合はメーカー・専門業者による点検をおすすめします。
主な原因③:ガスの種類
赤火の原因として見落とされがちなのが、ガスの種類がコンロの仕様と合っていないケースです。
ガスコンロには「都市ガス(13A)」用と「LPガス(プロパン)」用の2種類があり、それぞれでノズル径や燃焼空気の混合量が異なります。
このため、異なるガス種に接続してしまうと、ガスと空気の混ざり方が崩れ、不完全燃焼を起こして赤火になります。
実際の現場でも、引っ越しや中古住宅での再利用時にガス種を確認せずに取り付けた結果、火が赤くなったという相談が少なくありません。
特に都市ガスからLPガスに変更した場合は、ガス圧力や燃焼設計が大きく違うため、青火が維持できなくなります。
こうした状態では、炎の先が赤く揺らいだり、鍋底にススが付きやすくなるのが特徴です。
この場合は清掃では改善せず、適合するガス種用の機器に交換することが唯一の対処法です。
現場でも、「火はつくけれど赤くて勢いが弱い」という症状の裏に、ガス種の不一致が原因だったケースは珍しくありません。
コンロ背面や天板下のラベルに記載された「13A」または「LP」表記を確認し、使用するガス種と一致しているかをチェックしましょう。
主な原因④:経年劣化・バーナー部品の変形
長く使っているガスコンロでは、金属部品の劣化や変形が原因で赤火が発生することがあります。
特にバーナーキャップは、日々の点火・加熱によって高温にさらされ続けるため、10年前後の使用で金属が歪んだり、腐食で穴の形が変わったりすることがあります。
このわずかな変形によって、ガスと空気の混ざり方が乱れ、燃焼が不均一になって赤い炎が出るのです。
外見上はきれいに見えても、内部では熱膨張と冷却を繰り返すうちに金属疲労が進み、微細なひび割れやサビが発生していることも少なくありません。
特にステンレス製のバーナーであっても、湿気や油分が付着した状態で放置されると腐食が進み、ガスの噴出量が部分的に偏ることがあります。
現場では、次のような状態が見られたら交換のサインと判断しています。
- 炎の高さや色が左右で違う
- バーナー表面にサビ・焦げ・変色がある
- 清掃しても赤火が改善しない
- 使用時に“ボッ”という着火音がする
これらの症状が出ている場合は、単なる汚れではなく部品そのものの劣化が疑われます。
部品交換で改善するケースもありますが、使用年数が10年を超えている場合は、コンロ本体の交換を検討したほうが安全です。
現場でも「掃除をしても火が青くならない」という相談の多くが、内部腐食やバーナー変形によるものでした。
表面を磨くだけでは直らないため、無理に使い続けず、専門業者に点検を依頼しましょう。
赤火を放置するとどうなる?


赤火のまま使い続けると、見た目以上に深刻な影響を及ぼします。
赤い炎はガスが十分に燃え切っていない状態を示しており、そのまま使用を続けると一酸化炭素(CO)の発生やススの蓄積、機器内部の焼損など、複数のリスクが重なります。
まず注意すべきは一酸化炭素(CO)です。
不完全燃焼によって発生するこのガスは、無色・無臭で気づきにくく、少量でも長時間吸い込むと頭痛やめまいを引き起こすことがあります。
現場では「冬場に換気を控えたまま赤火の状態で調理していた結果、体調不良を感じた」という事例も報告されています。
小さな炎の色の違いが、思わぬ健康被害につながる可能性があるのです。
次に問題となるのがスス(煤)や焦げの発生です。
燃焼が不完全な状態では、炭素分が空気中に残り、鍋底や壁面に黒い汚れとして付着します。
このススは放置すると油汚れと混ざって落ちにくくなり、換気扇やレンジフードの効率も低下させます。
調理中に焦げたようなにおいが残るのも、このススが原因であることが多いです。
さらに、赤火が続くことでコンロ内部への熱負荷も増加します。
炎が安定せず、局所的に高温が集中することで、点火プラグやバーナーキャップが変形・破損するリスクが高まります。
結果的に、寿命を大幅に縮めてしまうことにもつながります。
現場でも、赤火を放置したことで「点火が不安定になった」「バーナーが変形して交換が必要になった」という例は珍しくありません。
外見では大きな異常がなくても、内部部品には確実に負担がかかっています。
赤火は“今すぐ火が止まる”ほどの異常ではありませんが、安全性・衛生面・機器寿命のすべてをじわじわと損なうサインです。
気づいた段階で早めに対処することが、結果的に機器を長持ちさせ、家族の安全を守ることにつながります。
自分でできる応急チェックリスト
赤火の原因には、掃除や確認だけで改善できるものも少なくありません。
ここでは、専門的な分解を伴わずにできる家庭での応急チェックポイントをまとめました。
一つひとつ確認しながら進めることで、炎の色を元の青火に戻せる場合もあります。
| チェック項目 | 確認方法 | 改善の目安 |
|---|---|---|
| バーナーキャップの汚れ | コンロの火口部分を外して目視。吹きこぼれや焦げが付着していないか確認。 | 穴が塞がっている場合は歯ブラシでやさしく清掃。 |
| バーナーの向き・位置ズレ | 清掃後にキャップを戻す際、向きや凹凸の位置が合っているか確認。 | 正しい位置に戻すと炎が安定しやすくなります。 |
| 鍋底の状態 | 焦げや油汚れが厚く付いていないか。 | 鍋底が汚れていると熱がこもり、赤火のように見えることがあります。 |
| 換気扇の運転 | 調理中に換気扇が作動しているか、吸い込み音が弱くないか確認。 | フィルターの目詰まりを掃除することで燃焼環境が改善。 |
| ガス種の確認 | コンロ側面または天板下のラベルに「13A」または「LP」表示を確認。 | 使用しているガス種と一致していない場合は交換が必要。 |
| 使用年数 | 購入・設置からの年数を確認。10年以上経過していないか。 | 長期使用は内部劣化の可能性が高く、点検・交換の目安です。 |
これらを確認しても炎が青く戻らない場合、内部部品の劣化や燃焼系統の詰まりが進行している可能性があります。
その場合は無理に使い続けず、専門業者に点検を依頼するのが安全です。
現場でも、上記のチェックを実施しただけで改善するケースは多く見られます。
特に「汚れ」「位置ズレ」「換気不足」の3点は、手軽かつ効果的なセルフ確認ポイントです。
よくある誤解:「赤火は冬のせいだから大丈夫」?


「寒い季節になると赤火になるのは普通ですよね?」――現場でもこうした質問をよく受けます。
確かに、外気温が下がる冬場は空気の流れや燃焼状態に多少の影響を与えることがあります。
しかし、赤火そのものを“季節のせい”にするのは誤りです。
家庭用のガスコンロは、気温や湿度の変化を想定して設計されており、正常な状態であれば真冬でも青火が保たれます。
つまり、赤火が続く場合には、他に原因があると考えるのが自然です。


その中でも冬に特に多いのが、「加湿器の使用による炎色反応」です。
加湿器の蒸気には、使用する水道水中のカルシウムやナトリウムなどの微量ミネラル成分が含まれています。
これらが燃焼中の炎に混ざると、化学的に炎が赤やオレンジ色に見える現象が起きるのです。
この場合、実際の燃焼は正常でも、見た目だけが赤く見えるため、
「赤火=不完全燃焼」と勘違いしてしまうケースが少なくありません。
加湿器をコンロ近くで使用しているときや、スチームがコンロに直接あたる位置に置いていると、特にこの現象が起こりやすくなります。
実際の点検でも、「冬だけ火が赤くなる」と相談を受けて現場へ行くと、
加湿器がコンロ横に置かれていた、というケースが非常に多く見られます。
加湿器を離して使用すると炎が青く戻ることも珍しくありません。
安全な対処法と業者に依頼すべきタイミング
赤火を見つけたときに大切なのは、慌てず原因を切り分けることです。
赤い炎が一時的な汚れや環境の影響によるものなのか、それとも機器内部の不具合なのかを見極めることで、正しい対応ができます。
まずは家庭でできる基本的な対処から始めましょう。
- バーナーキャップを清掃する
火口にこびりついた焦げや油汚れを歯ブラシなどでやさしく除去します。
水洗い後はしっかり乾燥させてから取り付けてください。 - 鍋やフライパンの配置を見直す
大きな鍋で炎口を覆ってしまうと、空気の流れが妨げられ不完全燃焼を起こします。
特に三口コンロで同時使用する際は、奥側の口を避けて空間を確保することが大切です。 - 加湿器やスチーム家電を離す
炎色反応で赤く見えることがあるため、加湿器はコンロから2〜3mほど距離を置きましょう。 - 換気扇を常時運転する
調理中は常に空気を循環させ、燃焼環境を安定させます。
レンジフードのフィルターに油汚れが詰まっている場合は清掃も有効です。
こうした基本的な対処を行っても赤火が改善しない場合は、機器内部に原因があると考えられます。
バーナーやガスノズルの詰まり、金属部の変形などは、見た目では判断できません。
構造部分に触れるとガス漏れや点火不良につながるため、自分で分解・調整するのは厳禁です。
実際の現場では、「掃除しても青火に戻らない」という相談の多くが、
内部の腐食やバーナー歪みによるもので、外からでは確認できないケースでした。
以下のような症状が続く場合は、早めに専門業者へ点検を依頼してください。
- 清掃後も炎の色が赤いまま
- 炎の一部が出ていない
- 点火時に「ボッ」と音がする
- ススや黒煙が出る
- 炎が左右で極端に違う
家庭での対処はあくまで応急対応にとどめ、継続する赤火は専門点検が必要なサインと考えるのが安全です。
FAQ(よくある質問)
Q1. 赤火は危険ですか?
A. はい。赤火は不完全燃焼を起こしているサインであり、放置すると一酸化炭素(CO)の発生やススの付着、部品劣化の原因になります。
一時的な変色なら問題ありませんが、長く続く場合は点検が必要です。
Q2. 赤火になったとき、まず何をすればいいですか?
A. まずはコンロを消火し、バーナーキャップを外して汚れや焦げを確認しましょう。
焦げ付きや油汚れが見られる場合は、歯ブラシで軽く清掃して乾燥させてから再点火してください。
改善が見られない場合は、専門業者による点検をおすすめします。
Q3. 加湿器を使うと赤火になるのはなぜですか?
A. 加湿器の水蒸気に含まれるカルシウムやナトリウムなどのミネラルが、炎の中で炎色反応を起こすためです。
燃焼状態そのものに異常はありませんが、見た目の色が赤〜オレンジに変化して見えることがあります。
加湿器はコンロから1〜2m離して設置するのが理想です。
Q4. 冬だけ火が赤くなるのは季節のせいですか?
A. いいえ。季節そのものが原因で炎が赤くなることはほとんどありません。
冬場は換気不足や湿度変化、加湿器の使用など、環境要因が重なりやすいため、結果的に赤火が目立つことがあります。
原因を特定するには、清掃・換気・機器確認の3点を行うのが効果的です。
Q5. 清掃しても直らない場合、修理と交換どちらが良いですか?
A. 使用年数が10年未満であれば、バーナーや部品交換で改善する可能性があります。
10年以上経過している場合は、内部劣化が進行していることが多く、本体交換を検討するのが安全です。
特に火力が不安定・異音がするなどの症状がある場合は、早めの判断が重要です。
✅ガスコンロのことはルーム・テック・ラキアにご相談ください


赤火は、コンロが「少し助けを求めている」サインです。
汚れや環境で一時的に赤くなることもありますが、長く続く場合は内部の不具合や劣化が進んでいることもあります。
ルーム・テック・ラキアでは、点火・燃焼・安全装置までを含めた総合的な点検・交換対応を行っています。
「火の色が気になる」「ススが出る」「掃除しても直らない」など、どんな小さな違和感でもお気軽にご相談ください。
地域に根ざした専門スタッフが、ご家庭に合わせた最適なご提案をいたします。
安全で快適なキッチンを守るために、まずはプロによる点検をご検討ください。



ご連絡をお待ちしております!


札幌・近郊の住まいに選ばれる施工店|ルーム・テック・ラキアのこだわり


丁寧な施工 -Installation-
- ベテラン職人による確実な施工
- 施工時の安全確認を徹底
- アフターフォローもしっかり対応


地域密着対応 -Service-
- 札幌市内・近郊を中心に迅速対応
- 担当者の顔が見えるから安心
- 急なトラブルもご相談ください
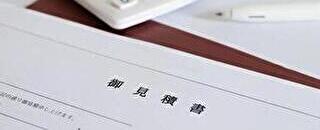
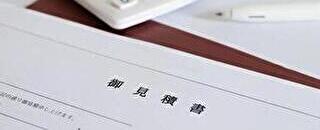
安心価格 -Price-
- 施工前の安心見積
- 各費用込みの標準工事費
- 工事後の追加請求なし
対応エリア
札幌市内全域(中央区・北区・西区・南区・東区・白石区・清田区・厚別区・豊平区・手稲区)
札幌市近郊
北広島市/恵庭市/江別市/小樽市/石狩市/千歳市
当別町/南幌町/長沼町/岩見沢市/苫小牧市
※その他の地域についてはご相談ください。